建設業
CCUS
コンプライアンス
労働災害防止のため、免許・技能講習、特別教育が必要な業務について
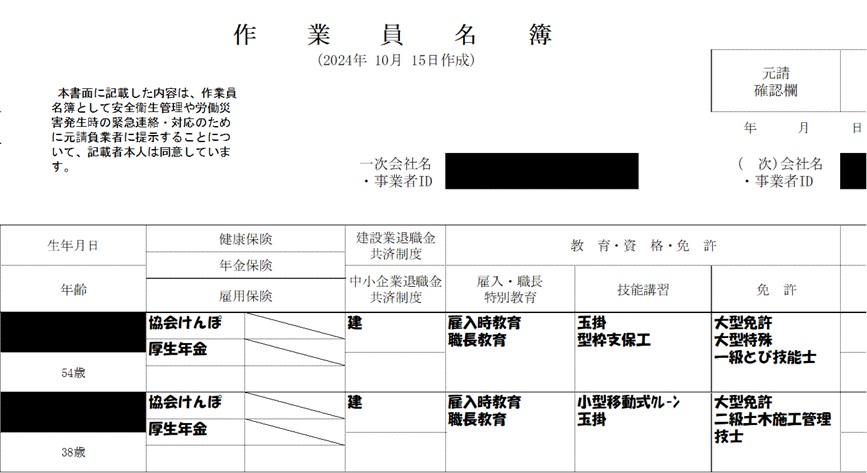
投稿日 2025年5月6日 最終更新日 2025年5月6日
労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、免許の取得や技能講習の修了など就業の制限(就業制限業務)が設けられている場合があります。また、業務によっては、一定の資格を有しているものを作業主任者として選任することが求められたり、作業員に特別教育を受けさせることを義務付けている場合があります。
複雑で解りづらい制度ですが、特に建設業において、これらの対象業務となっているものが多いため、どのような場合に有資格者の配置や教育が必要になるのか整理してみます。
1.作業主任者の選任(安衛法14条)
政令(6条)で定める危険又は有害な作業を行う場合には、作業員を直接指揮する作業主任者(※1)の配置が必要になります。作業主任者は、作業の内容に応じて、都道府県労働局の登録を受けた教習機関が行う技能講習を修了した者又は指定試験機関が行う免許試験に合格した者の中から、事業者が選任し、その者に労働者の指揮、その他労働災害防止のための法定事項を行わせなければなりません。(事業場の規模は問いません)
※1.職長との違い:職長は現場の作業者を直接指揮・監督する立場ですが、作業主任者は特定の危険な作業を安全に実施する立場となるので、同一現場であっても他の作業箇所との兼任は認められません。
2.就業制限(安衛法61条)
政令(20条)で定める特定の危険な業務については、就業制限業務として、資格を有する者(登録教習機関が行う技能講習を修了した者又は指定試験機関が行う免許試験に合格した者)以外が就労することが禁止されています。
3.安全衛生教育の実施(安衛法59条)
■雇い入れ時教育の実施(第1項)、作業内容変更時の教育の実施(第2項)
業種・職種・雇用形態などにかかわらず、事業者は、労働者を新たに雇い入れたり、その作業内容を変更したときは、遅滞なく、安全衛生教育を実施しなければなりません。この教育は、労働安全衛生規則第35条にもとづき事業者が行うものとされています。
※教育の内容☞厚生労働省「省令(35条)で実施すべきとされている労働安全衛生教育」
■特別教育の実施(第3項)
一定の危険・有害な業務(省令(36条)で定める49業務)に労働者を就かせるときは、事業者は、その業務に関する安全または衛生に関する特別の教育(特別教育)を行わなければなりません。
特別教育の内容や時間については、厚生労働省が定める「安全衛生特別教育課程」にもとづき事業者が行うものとされていますが、外部機関(都道府県労働局の登録は不要)が実施する特別教育を受講させることも可能です。
なお、特別教育を実施したときは、教育の受講者、科目等を記録し、3年間保存しなければなりません。
4.職長教育(安衛法60条)
事業者は、その事業場の業種が政令(19条)(※2)で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。※1)に対し、以下の事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければなりません。なお、職長教育は、事業者が自ら実施するほか、外部機関(都道府県労働局の登録不要)が実施しているものを受けさせることもできます。
- 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
- 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
- 上記のほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
※2.職長教育を行うべき業種:①建設業 ②製造業(たばこ製造業、繊維工業、衣服その他の繊維製品製造業、紙加工品製造業などを除く) ③電気業 ④ガス業 ⑤自動車整備業 ⑥機械修理業
5.その他、安全衛生責任者教育など
労働安全衛生法に基づく教育は、上記以外にも「危険有害業務従事者への教育」「安全衛生業務従事者に対する能力向上教育」などがあるほか、通達において「安全衛生責任者(※3)」、「振動工具取扱い作業者」、「騒音職場の作業者」、「VDT作業従事者」、「重量物取扱い作業、介護・看護作業、車両運転作業等の従事者(腰痛予防の教育)」などに対する安全衛生教育が示されています。
※3.安全衛生責任者は、特定元方事業者が統括安全衛生責任者を選任しなければならない場合(労働者数100人以上の工事)に、関係請負人(下請事業者)が選任する責任者です。安全衛生責任者に対する教育は、事業者が自ら実施するほか、外部機関(都道府県労働局の登録不要)が実施しているものを受けさせることもできます。安全衛生責任者には職長が選任されることが多いことから、外部団体において「職長・安全衛生責任者教育講習」が準備されています。
6.免許・技能講習・特別教育が必要な業務の一覧
免許・技能講習(作業主任者講習を含む)・特別教育が必要な業務の一覧については、下記リンクを参考にしてください。
なお、業務によっては、要求される資格に段階があるもの(例・クレーン運転の場合、つり上げ荷重5t以上→免許、5t未満1t以上→技能講習、1t未満→特別教育)がありますが、その場合は上位の業務の資格を持っていれば、下位の業務を実施することが可能です。
☞厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」
☞JISHA中央労働災害防止協会「各種安全衛生教育一覧(簡易チェックリスト)」
7.【参考】解体工事を行う場合の(安衛法に定める)資格等取得の例
| 作業主任者及び作業者 | 業務内容 | 免許 | 技能講習 | 特別教育 |
| 移動式クレーン運転者 | つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転 | 〇 | ||
| 〃 | つり上げ荷重が1t以上5t未満の移動式クレーンの運転 | 〇 | 〇 | |
| 〃 | つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの運転 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 玉掛け作業者 | 制限荷重が1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t以上のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 〇 | ||
| 〃 | 制限荷重が1t未満の揚貨装置又はつり上げ荷重が1t未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛け | 〇 | ||
| 車両系建設機械(整・運搬・積込み・掘削用)運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t以上のもの | 〇 | ||
| 〃 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t未満のもの | 〇 | ||
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t以上のもの | 〇 | ||
| 〃 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t未満のもの | 〇 | ||
| 基礎工事用建設機械運転者 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 | 〇 | ||
| 車両系建設機械(解体用)運転者(ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機) | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t以上のもの | 〇 | ||
| 〃 | 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転の業務。ただし、道路上の走行を除く。機体重量3t未満のもの | 〇 | ||
| ガス溶接作業者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱の作業 | 〇 | ||
| 〃 | 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務 | 〇 | ||
| 〃 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | 〇 | ||
| 足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 〇 | ||
| 足場の組立て作業等作業 | 足場の組立て、解体又は変更の作業にかかる業務 | 〇 | ||
| 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 | 〇 | ||
| 木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地、外壁下地の取付けの作業 | 〇 | ||
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 〇 | ||
| フルハーネス型墜落制止用器具 | 高さが2m以上の個所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業にかかる業務 | 〇 | ||
| 石綿作業主任者 | 特定石綿等を製造し、又は取り扱う作業 | 〇 | ||
| 石綿取り扱い作業者 | 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業 | 〇 |
【上記以外】
| 作業指揮者 | 木造建築物の解体 | 木造建築物解体工事作業指揮者安全衛生教育(受講は任意) |
| 振動工具取扱作業者 | 建物や構造物の解体において使用される振動工具(ハンドブレーカー、破砕機など) | 振動工具取扱作業者安全衛生教育(受講は義務) |
| 職長・安全衛生責任者 | 職長・安全衛生責任者教育(受講は任意) |
建設業の許可やCCUSの登録申請をお考えの場合は、弊所にご相談ください!



